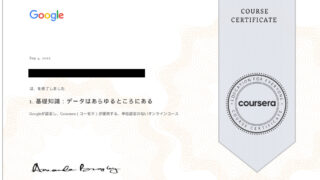はじめに
次のような悩みありませんか?
- 「ChatGPTは使いこなせるのに、AWS上での生成AIになると難しそう…」
- 「Amazon Bedrockの使い方や設定がわからない」
- 「社内データを使いたいけど、セキュリティが不安…」
- 「生成AIを業務システムと連携したい」
- 「実例がないとイメージが掴めない」
まさに“これらの壁”を超えるための1冊がこの本です。
総評
対象読者
●AWS利用経験はあるけど生成AIはあまり詳しくないエンジニア
●生成AI導入を考えている情シス担当者
●生成AI導入を検討するAI推進リーダー/マネージャー
●生成AIを社内業務に展開したい人
書籍内容(抜粋)
第1章 「生成AI」の基本と動向
- 人工知能(AI)と生成AIの位置付け
- 「モデル」に関する基礎知識
- ChatGPT
- Stable Diffusion
- GitHub Copilot
- 生成AIのAPI提供とクラウドへの展開
第2章 Amazon Bedrock入門
- 対応AWSリージョン
- Bedrockのモデル利用料金
- なぜAWSのBedrockを選ぶのか
- Anthropic社の生成AIのモデル
- Cohere社の生成AIのモデル
- Command Rシリーズ
- Stability AI社の生成AIのモデル
- SDXL 1.0
- Titan Text G1 – Premier
- Titan Text G1 – Express / Light
- Titan Text Embeddings V2 / G1-Text
- Titan Multimodal Embeddings G1
- Titan Image Generator G1
- Meta社の生成AIのモデル
- Mistral社の生成AIのモデル
- Mistral Large / Small
- Mixtral 8×7B Instruct
- Mistral 7B Instruct
- AI21 Labs社の生成AIのモデル
- ハンズオン Bedrockを実際に試してみよう
- プレイグラウンドを利用してGUI上で生成する方法
- AWS SDKを用いて各モデルのAPIへリクエストを行う方法
第3章 生成AIアプリの開発手法
- プロンプトとは
- トークンとは
- 文字列のトークンへの分割
- トークン数の算出方法
- プロンプトエンジニアリングとは
- 生成AIアプリ開発に使用する主要なフレームワーク
- LangChain
- Streamlit
- ハンズオン LangChainとStreamlitを使った生成AIアプリ開発
- ステップ1 LangChainの実装
- ステップ2 ストリーム出力
- ステップ3 Streamlitとの統合
- ステップ4 チャット形式の継続したやり取り
- ステップ5 チャット履歴の永続化
- ハンズオン AWS Lambda上で動作する生成AIアプリ開発
- AWS Lambdaを採用した生成AIアプリ
- 構築内容
- Lambdaレイヤーを作成する
- Lambda関数を作成する
- 生成AIアプリ開発に使用するその他のフレームワーク
- LlamaIndex
- Gradio
- Chainlit
- Dify
- LiteLLM
第4章 社内文書検索RAGアプリを作ってみよう
- RAGの特徴とユースケース
- 意味検索を可能にする「埋め込み」
- ハンズオン Knowledge BasesでRAGを実装してみよう
- Knowledge Basesの仕組み
- Knowledge Basesを利用したRAGアプリ開発の概要
- S3バケットを作成する
- ナレッジベースを作成する
- モデルを有効化する
- ナレッジベースの単体動作を確認する
- フロントエンドを実装する
- RAGアプリケーションを実行する
- 不要リソースの削除方法
- Knowledge Basesのクエリ設定
- Knowledge Basesの利用料金
- Amazon OpenSearch Service
- Amazon OpenSearch Serverless
- Amazon Aurora & RDS
- Amazon DocumentDB
- Amazon MemoryDB for Redis
- Pinecone
- Redis Enterprise Cloud
- MongoDB Atlas
- Amazon Kendra
- Amazon DynamoDB
- Amazon S3
- お勧めのRAGアーキテクチャ例
- RAGの回答品質を上げるための工夫
- チャンクサイズの調整
- メタデータの追加
- リランク
- RAGフュージョン
- Rewrite-Retrieve-Read
- HyDE
- RAGアプリケーションの評価ツール
- Ragas
- LangSmith
- Langfuse
第5章 便利な自律型AIエージェントを作ってみよう
- 高度なAIエージェントの実現手法「ReAct」とは
- オープンソースのAIエージェント
- AIエージェントのユースケース
- ハンズオン LangChainでAIエージェントを実装してみよう
- ハンズオン① ツールを利用するAIエージェント
- ハンズオン② ReActエージェント
- Agents for Amazon Bedrockとは
- Agentsの仕組み
- Agentsの詳細
- 対応モデルとリージョン
- Agentsの使用料金
- ハンズオン AgentsでAIエージェントを作ってみよう
- モデルを有効化する
- Pineconeを準備する
- S3バケットを作成する
- ナレッジベースを作成する
- Lambdaレイヤーを作成する
- Agentsを作成する
- アクショングループを追加する
- Lambda関数を設定する
- ナレッジベースを追加する
- エイリアスを作成する
- 動作確認
第6章 Bedrockの機能を使いこなそう
- カスタムモデル
- ファインチューニング
- 継続的な事前トレーニング
- カスタムモデルインポート
- セーフガード
- ウォーターマーク検出
- ガードレール
- 評価と導入
- モデル評価
- プロビジョンドスループット
- Bedrockのその他の機能
- バッチ推論
- Bedrock Studio
第7章 さまざまなAWSサービスとBedrockを連携しよう
- Amazon CloudWatchとの連携
- CloudWatch Metrics
- CloudWatch Logs
- AWS CloudTrailとの連携
- 管理イベントとデータイベント
- WS PrivateLinkとの連携
- PrivateLinkの概要
- 生成AIアプリのネットワーク設計
- AWS CloudFormationとの連携
- Amazon Aurora
- Amazon CodeCatalyst
- Amazon Lex
- Amazon Transcribe
- Amazon Connect
第8章 生成AIアプリをローコードで開発しよう
- AWS Step Functionsとプロンプトチェイニング
- Step Functionsとは
- 統合の種類
- プロンプトチェイニングとは
- Workflow Studioの使い方
- JSONPath構文を使った値の参照と組み込み関数
- ハンズオン BedrockとStep Functionsを使った生成AIアプリ開発
- 手順1 Bedrockに関する投稿を取得する
- 手順2 取得した投稿の要点をまとめる
- 作成したタスクをテスト実行する
- 手順3 自己紹介文とキャッチコピーを作成する
- 手順4 生成したものをMarkdown形式に変換する
- 手順5 アイキャッチ画像を生成する
- 完成したステートマシンを実行する
- 確認画面を作成する
第9章 Bedrock以外の生成AI関連サービスの紹介
- AWSの生成AIスタックの種類
- 生成AIをアプリケーションとして利用したい
- Amazon Q
- PartyRock
- AWS HealthScribe
- 生成AIモデルの学習・推論インフラがほしい
- Amazon SageMaker
- Amazon SageMaker JumpStart
- Amazon SageMaker Canvas
- AWSの独自設計チップ
- ハンズオン Amazon Q Businessアプリ開発
- RAGに使用するドキュメントの準備
- AWS IAM Identity Centerの作成
- Amazon Q Businessアプリにサインインするユーザーの作成
- Amazon Q Businessアプリの作成
- Amazon Q Businessアプリの構成確認
- Amazon Q Businessアプリのオプション設定
- ハンズオン環境の削除
第10章 Bedrockの活用事例
- KDDIアジャイル開発センターの事例
- Relicの事例
- 富士ソフトの事例
第11章 お勧めの最新情報のキャッチアップ方法
- AWS公式コンテンツ
- 公式ドキュメント
- AWS What’s New
- AWSブログ
- AWS Japan公式コンテンツ
- AWS Black Belt オンラインセミナー
- 週刊AWS
- builders.flash
- AWS Innovate
- AWS Hands-on for Beginners
- JP Contents Hub
- 目的別クラウド特化型と概要料金例
- GitHub 公開コンテンツ
- 技術コミュニティ
- JAWS-UG (AWS User Group – Japan)
- StudyCo
- ChatGPT Community (JP)
- 情報発信&収集プラットフォーム
- Qiita
- X(旧Twitter)
- Discord
付録
- 付録1 AWSアカウントの作成手順
- AWSアカウントを作成する
- MFA(多要素認証)を設定する
- 付録2 IAMユーザーの作成手順
- IAMユーザーを新規作成する
- MFA(多要素認証)を作成する
- 付録3 Cloud9用VPCの作成手順
- VPCを作成する
- 付録4 Cloud9の作成手順
- Cloud9を作成する
- Python開発の環境を設定する
書籍のポイント
本書の中でも特に注目すべき4つのポイントを紹介します。
Amazon Bedrockは、AWSが提供する“本番運用できる生成AI基盤”
生成AIを安全に企業利用したい人にとって、注目すべきなのが Amazon Bedrock(ベッドロック) です。
AWSが提供するマネージド型の生成AIプラットフォームで、テキスト生成・画像生成・要約・検索などをクラウド内で完結させることができます。
Bedrockの最大の魅力は、複数のAIモデルを統一環境で使える点
AnthropicのClaude、MetaのLlama 3、Stability AIのSDXLなど、世界最先端のモデルをAPIひとつで自由に切り替えられるのです。
これにより、企業は自社データを外部に出さず、セキュアに生成AIを活用できます。
本書の第2章「Amazon Bedrock入門」では、以下のような知識をステップ形式で学べます。
- Bedrockの仕組みと導入メリット
- 各モデル(Claude、Llama、Titanなど)の特性と選び方
- AWS上での運用設計(セキュリティ・コスト・スループット)
AWS環境で安全に生成AIを活用する道筋を掴めます。
RAG × Knowledge Basesで社内検索AIを構築しよう
多くの企業が最初に直面する壁が、「自社データを安全に使えるAI」の構築です。
ここで注目されているのが、RAG(Retrieval-Augmented Generation) という仕組み。
Bedrockでは「Knowledge Bases」を使うことで、このRAGをAWS環境の中で安全に実装できます。
RAGとは、生成AIが回答を出す前に社内ドキュメントを検索・要約して参照する仕組みのこと。
これにより、AIが「会社固有の知識」に基づいて答えを生成できるようになります。
Knowledge Basesは、Bedrock専用のRAG基盤です。
S3にアップロードしたドキュメントを自動でベクトル化し、ClaudeやTitanなどのモデルからクエリを投げるだけで、意味検索 → コンテキスト生成 → 回答出力 まで自動的に行ってくれます。
しかも、AWSのセキュリティ境界内で動作するため、情報漏洩や外部API依存の心配がありません。
管理者はIAMでアクセスを制御し、CloudTrailで操作ログを監査可能。企業利用に必要なガバナンスが標準で整っているのです。
本書第4章「社内文書検索RAGアプリを作ってみよう」では、以下のポイントを実際のハンズオン形式で学べます。
- Knowledge basesを使ったRAGの設定手順
- 検索対象サービス(Kendra、Pinecone、DynamoDBなど)の比較
- 回答精度を上げるコツ(チャンクサイズ・メタデータ設計・リランク)
- RAGアプリの品質評価ツール(Ragas、LangSmith、Langfuse)
BedrockのGUIだけで社内検索AIを作る流れが具体的にわかるため、「ノーコードでもAI活用したい情シス担当者」にも最適です。
LangChain × Bedrock × AgentsでAIエージェント開発
生成AIは、いま“答えるAI”から“行動するAI”へと進化しています。
その中心的存在が AIエージェント(AI Agent) です。
AIエージェントとは、与えられた目的に応じて自らツールを選び、情報収集・分析・実行までを自動で行う知的システムのこと。
本書第5章では、そんなエージェントをLangChain × Bedrock の組み合わせで実装する方法が詳しく紹介されています。
LangChainはプロンプト設計や外部ツール連携を得意とするPythonフレームワーク。
BedrockのClaudeやTitanなどのモデルをLangChain経由で呼び出すことで、「計画→実行→検証」を自動で繰り返す自律型AIを構築できるのです。
さらに注目したいのが、AWS純正の自律AI開発環境Agents for Amazon Bedrock。
この機能を使えば、LangChainのようにコードを書かなくても、AWSコンソール上でGUI形式のAIエージェントを作成可能です。
たとえば、S3・DynamoDB・Pineconeと連携して、「社内データを自動分析し、結果を要約してSlackへ送る」といったタスクを、数クリックで自動化できます。
しかも、IAM認証・CloudWatchログ・Lambda連携など、AWSのガバナンス体系と統合されているため、企業利用でも安心して運用できる点が大きな魅力です。
第5章「便利な自立型AIエージェントを作ってみよう」では、以下のステップでエージェント開発を学びます。
- LangChainでツール利用型エージェントを構築
- ReAct(推論+行動)パターンによる高度エージェント開発
- Agents for Bedrockによるノーコード構築手順
- LambdaやS3を使ったタスク連携の設定
特に、BedrockとLangChainを組み合わせたサンプルコードは、即ビジネスPoCで再利用できるレベルの完成度です。
Step Functionsでローコード開発!AWS生成AIを自動化
生成AIの可能性を感じていても、「コードを書くのは難しそう」と感じている人は多いでしょう。
そんな人にこそ知ってほしいのが、AWS Step Functions × Bedrock の組み合わせです。
Step Functionsは、AWSのローコード自動化ツール。
フローチャートのように処理をつなげていくことで、複雑なAIアプリの流れを視覚的に設計できます。
本書第8章では、このStep FunctionsとBedrockを連携させ、テキスト生成 → 要約 → 画像生成までを自動化するハンズオンが丁寧に紹介されています。
Step Functionsの強みは、Bedrockのモデルを含め、他のAWSサービスを自在に組み合わせられる点です。
例えば、次のような流れをGUIだけで作れます。
- Bedrockで記事を生成
- 要約
- 要約をMarkdownに変換
- アイキャッチ画像を生成
これらをワークフローとして保存すれば、ボタン一つで自動記事生成AIを完成させられます。
第8章「生成AIアプリをローコードで開発しよう」では、以下の流れを具体的な手順で解説しています。
- Step Functionsの基本構造と統合方法
- Bedrockを組み込んだステートマシンの設計
- 生成AIの処理をタスク化して自動実行
- 出力(テキスト・画像)をアプリに連携
AWS初心者でも、UI操作を追うだけで実際に動く生成AIワークフローを構築できる構成になっています。
まとめ
「Amazon Bedrock 生成AIアプリ開発入門」は、単なる技術解説書ではありません。
この本は、企業が本気で生成AIを業務に取り入れるための地図です。
ソースコードもあるし、基本から実践まで書いてあるので、ばりばりの技術者でなくても読める内容になっています。
第1章〜第3章では、Bedrockの全体像からモデル選定、LangChain・RAGなどの開発基礎を体系的に理解できます。
そして、第4章以降では、実際にAWS上で動くアプリを作るハンズオンが満載。
「読むだけ」ではなく、「手を動かすことで学べる」のが本書の最大の魅力です。
この本を読むことで得られる“3つの変化”があります。
①生成AIを理解する立場から、実装できる立場へ
Bedrockのモデル構成、API操作、RAG実装など、抽象的だった生成AIの仕組みが手に取るようにわかります。
②自社データを安全に活かす方法が見える
Knowledge basesやAgentsの章で、セキュリティを確保しながらAI活用する設計が学べます。
③AI活用を組織に広げるビジョンが描ける
Step FunctionsやAWS連携の章を通じて、ノーコードでも実現できるAI導入の道筋が見えます。
Amazon Bedrockは、企業が生成AIを“業務インフラ”として扱う時代の要です。
本書は、その未来を最短で実現するためのガイドブックです。